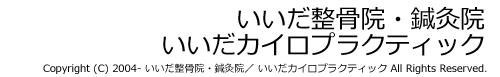ダイハードでマッチョな刑事だったブルース・ウイリスが小児精神科医マルコム・クロウのシリアスな役どころを好演するが、なんといってもコール・シアー役で主演のハーレイ・ジョエル・オスメント少年がいい。 死者が見えるという真実を人に告げることもできず、他人が納得するように嘘も付かねばならない。恐怖に打ち震え、いじめに耐え、周りからは情緒不安定なやつだと思われる。 そんな難しい役どころを、なんともいえない表情で演じて見せる。そっとやさしく抱きしめてやりたくなる、けなげな少年がそこにいる。
M.ナイト・シャマラン監督は、この映画で恐怖とどうコミュニケートするかを描きたかったという。 目の前に現れる死者達にただただ恐れおののいていたコール少年が、マルコム医師の援助で彼等とコミュニケート出来るようになった時に死者達が見えるという状況は変わらないにもかかわらず恐怖は克服されていく、癒されていく。 恐怖は自らが作り出しているものだということが納得できる。逃げようとすればするほど、考えまいとすればするほど、恐怖は大きなものになる。その恐怖に立ち向かう勇気を持った時に恐怖は消えていく。 コール少年の見る死者達を愛おしくさえ思えるようになったのは私だけだろうか。
人とコミュニケート出来ない恐怖も描く。マルコム医師と妻とのコミュニケートできない恐怖、夫婦間の溝がある。この恐怖は映画の冒頭で「この映画の“秘密”を話さないように」と釘を刺された秘密に密接に関係がある。 その秘密は見終わった後に自ら「絶対に話さないぞ」と心に誓ってしまうほどの秘密ではある。
コール少年とマルコム医師、母、教師、クラスメート達とのコミュニケート出来ない不安、悲しさは現在の我々のものだ。驚かされたのは、あのおどおどしたコール少年の内側にあった強さだ。 少年は自らが自らを癒すことでそれらの不安、悲しみを克服し、母の亡き祖母との確執を癒し、マルコム医師の妻との問題さえも癒してしまう強い力を秘めていた。 マルコム医師から習った手品をいじめっ子に見せるシーンに少年のしたたかさが描かれていることが“秘密”を知った後に判る。人には本来的に癒しの力が備わっていることを強く認識させられる。
頭の半分を銃で吹き飛ばされた少年が歩く、絞首台にぶら下がった男女の視線が我々を見据える。そんなシーンもあるがこの映画はホラー、オカルトではない、良質な心理劇だ。 こんな陳腐と思える演出が必然なのだとこれも“秘密”を知ると判ってくる。
もう一度トキワ劇場に行こう。より深く癒されに、“秘密”に至るヒントを確かめに。“秘密”を守るため妻とコミュケート出来ない状態を解消するため、今度は妻を引き連れて。 そして妻との溝を埋めるための絶好の機会となるだろう期待を胸に抱いて。